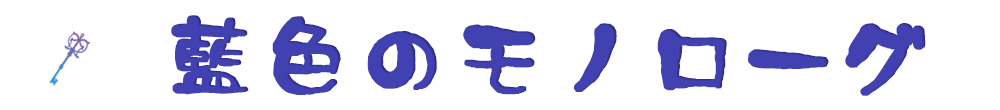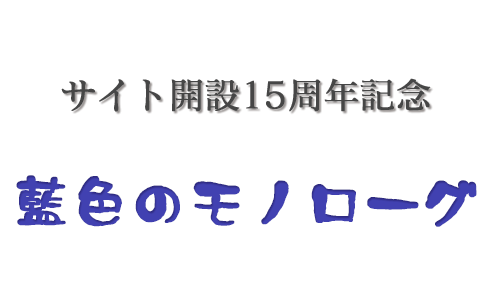before white minds
旋風にさよなら
「リンさんが戻ってきてるなんて知りませんでした」
「誰にも言ってなかったの。すぐにサホのところに飛んで来ちゃった」
家の中を片付けておいてよかった。ひっそりと安堵しながら、私はリンさんを居間に残して茶棚に向かった。自然と足取りが軽くなっていたみたいで、お気に入りのスカートや緩く編んだ髪が揺れる。「急に時間ができたの」って笑うリンさんの声が何だか懐かしかった。
リンさんの『気』は綺麗で凛として清らかで、傍にいるだけで私の気持ちも澄んでいくような心地になる。それをあえて隠していたのは、びっくりさせるつもりだったのか。いや、今だってその気を小さく抑え込んでいるのは、余計な人に気づかれたくないのかもしれない。
人間なら誰しも持っている気というものには個性がある。でも技使いの気は強いし、リンさんくらいになると『温度』や『感触』が違う。普通の人には理解できないみたいだけど、技使いにとっては強烈な違いだ。リンさんの気ならすぐに覚えられるって人も多いだろう。もしかすると、帰ってきたといっても短期間なのかもしれない。
「びっくりしましたよ。でも嬉しいです」
そんな大切な時間を私のために割いてくれたことは、とても幸福だ。辛いことはたくさんあったけれど、その度にリンさんが支えてくれた。最後まで、リンさんは私に力をくれるらしい。
それならせめてもてなさなきゃと、茶棚をのぞき込んだ私は顔をしかめた。新しい茶葉を買ってなかった。リンさんが宮殿へと出向いてから、この辺の技使いたちが集まる「お茶会」もどんどん数が減ってしまった。この間ナミアさんの家でやったのが最後かな。
誰も何も言わなかったけど、やっぱりリンさんの存在は大きい。ただ単に強い技使いというだけじゃあない。私たちを引っ張っていってくれる頼もしい人だ。私とはたった二つしか違わない、まだ十八歳の女の子なのに、その差は歴然としている。
「すみません、リンさん。リンさんの好きなお茶がなくて――」
「そんなのいいのいいのー! 宮殿だとまともなお茶一つ飲めなかったんだから、気にしないでっ」
振り返って謝罪を口にしようとすれば、途中で遮られた。この家唯一の小さなテーブルについたリンさんは、こちらを見てぱたぱたと右手を振っている。
リンさんが動く度にふわふわと揺れる黒い髪が好き。大きな黒い瞳が輝くのも、柔らかく細められるのも好き。ずいぶんと昔、同じ色に染めたいって言ったら止められたっけ。「せっかく綺麗な銀色なのに!」って。
「宮殿でのお勉強って、そんなに大変なんですか」
いつまでも過去にばかり浸っていてもいけない。お茶の準備を始めながら、私はそう尋ねた。リンさんが宮殿に呼ばれたのは、夏が過ぎた頃だった。『ウィンの旋風』なんて異名までついている、有名な技使いであるリンさんが、まさか神技隊に選ばれるとは誰も思っていなかった。私もしばらく信じていなかった。
神技隊というのは、異世界へ派遣される技使いの集団の名だ。
炎、風、水、あらゆるものを操ることができると言われる――実際は、そんなことないんだけど――技。それが使える人間が技使い。でもそんな技を異世界で何に役立てるというのか。全くわからないけれど、宮殿からの呼び出しを断れる人はまずいない。ウィンの長でさえそうなのだから、リンさんは言うまでもなかった。
「勉強も大変なんだけど、宮殿の人たちって愛想が悪いのよね。それに、本当に最低限のものしか用意してくれないの。お茶が出てこないどころか、お茶を淹れられるところも利用させてくれないのよ? ひどいわよねー」
よく使っていたカップを棚から取り出せば、背後からリンさんの愚痴が聞こえてくる。この世界の中心的役割を担っている宮殿が閉鎖的な場所であると聞いたことはあったけど、そういう問題もあるのか。
異世界へ行くためには異世界のことを学ばなければならない。その準備のために、リンさんはしばらく宮殿に住み込んでいた。実際に神技隊として異世界に派遣されるのは春の予定だ。それまでずっと宮殿なのか、たまにはこうして帰ってくることができるのか。それはたぶん、リンさんにもわからないんだろうな。
「それは不親切ですね」
とぽとぽとカップにお茶を注げば準備完了。そのまま盆に乗せ、私はリンさんのもとに向かう。するとリンさんはじっと私のことを見つめてきた。
「……どうかしました?」
「ううん。サホの気はやっぱり優しくて穏やかでいいなぁって思って」
青い花が描かれたカップをテーブルに置くと、リンさんの顔がほころんだ。リンさんはいつだって素直に何でも褒めてくるし好きだと言ってくるから、たまに恥ずかしくなる。でもおかげで小さな子たちは好意を口にするのに抵抗がないみたいだ。私はまだちょっと照れるけれど、でもリンさんの言葉になら答えられる。
「私、サホの気が大好きよ」
リンさんが『旋風』だなんて呼ばれているのは、強い風の技が使えるからじゃあない。それだけが理由じゃない。リンさんの影響力は、とにかく強かった。
「ありがとうございます。私もリンさんの気が好きですよ」
気は、私たちにとっては音のようなものだ。感じ取ろうと思わなくても勝手に飛び込んでくるし、そこから気分まで読み取れる。個性まであって、それで誰のものか判別できる。私はずっとリンさんみたいな気に憧れていた。――いや、リンさんそのものに憧れていた。
「みんな元気?」
嬉しそうにカップを手に取りながら、リンさんはそう続けた。みんなと聞いてぱっと思い浮かぶ顔ぶれは、大体この辺に住んでいる技使いたちだ。私もゆっくり席に着き、お盆を脇に除ける。
「はい、みんな元気ですよ。中には拗ねている人もいましたが」
「あーそう。うん、聞かないでおくわね」
「じゃあ言いませんね」
リンさんは一瞬だけうろんげな目をした。聞きたがらないってことは予想できてるってことだろう。それならば私もあえて教えたりはしない。せっかくリンさんが遊びに来てくれたんだから嫌な空気にはしたくない。
「それより、神技隊の仲間の方はどうでした?」
だからあえて話題を変える。もちろん、純粋な興味もあった。神技隊は五人の技使いで構成されていると、以前リンさんから聞いた。リンさんと一緒に仕事をすることになる技使いたちってどんな人なんだろう。やっぱりみんな強いのかな。
「みんないい人たちだったわよ。あ、いや、面白い人って言った方が正しいかも」
「面白い人……」
「あーそうそう、聞いて! なんとヤマト三人組の一人がいたんだから!」
それをどう受け取っていいのかわからず相槌を打っていると、リンさんはぱっと顔を輝かせた。カップへ伸ばそうとしていた私の手がつい固まる。たぶん、一瞬思考も止まっていた。それからようやく事態を飲み込んで、私は息を呑んだ。
「それって……」
「異名持ちに会ったのなんて初めてよ。びっくりしちゃった」
うんうん首を縦に振るリンさんに、あなたもその異名持ちですと指摘してよいのかどうか。私はしばらく逡巡した。
ヤマト三人組の噂なら耳にしている。ヤマト地方に住んでいる年の近い三人の技使いは、その力も拮抗していた。その一人がヤマトの若長であることも有名だ。私たちよりも少し年上で、二十歳は超えているはずだと記憶していた。
「確か、去年ヤマトの若長が選ばれてませんでした?」
「そうよ。さっすがサホ、よく覚えてるわね」
「そりゃあ忘れませんよ。大事件でしたよ。だから今年リンさんに声が掛かって、さらに驚いたんじゃないですか」
宮殿はヤマトの至宝まで持っていくつもりだ。そんな薄暗い噂も流れていた。「次は旋風か? まさかな」なんて悪い冗談を聞いたこともあった。それが現実のものになるとは、誰が予想できただろう。
「でもヤマト三人組と旋風が同じ隊に選ばれてるなんて、お仲間の方は驚いてませんでした?」
私はカップを手に取って、穏やかな香りを吸い込む。これでちょっとは落ち着ける。古い茶葉だから心配したけれど十分よい匂いだった。これは確かすずりちゃんが好きなお茶だったかななんて考えながら、まずは一口味わう。少し薄かったかな?
「え、全然。だって私、旋風だなんて言ってないもの」
けれども続くリンさんの言葉に、私は思わずむせそうになった。カップの中身までこぼしそうになってさらに慌てる。急いでカップをテーブルに置くと、私はまじまじとリンさんの顔を見上げた。
「言ってないんですか!?」
「自分で言うようなことじゃあないでしょう? 知らなくても全然問題ないし」
「そんな、後で知ったらきっと皆さんびっくりしますよ!?」
私としては珍しく、つい声が大きくなった。『旋風』の異名とその実力については、アール地方にいる知り合いも耳にしていたくらいだ。神技隊に選ばれるような技使いならまず間違いなくその名を知っているはず。でも確かに、『旋風』の容姿までは伝わってなかったかもしれない。性別すら曖昧なようだった。
「そうかなぁ?」
カップを見下ろしたリンさんは至極不思議そうな顔だ。ぶんぶん首を縦に振った私は、そこで内心はっとした。ひょっとしてリンさんは『旋風』から解放されたいんじゃないだろうか?
私たちを守るための盾となり、様々な注目を引き、それでいて自由のために戦っていたリンさんだって、いい加減その名前から解き放たれたいはずだ。私たちだってそろそろ、リンさんの庇護に甘えているわけにもいかなくなった。
リンさんがいない今日までの日々で、そんなことを考えた。――どこにいたってリンさんの加護は感じられたけれど。
「別に秘密にしたいわけじゃないのよ。でも、あそこで私が自ら『旋風です』だなんて言ったら、対抗してるか自慢してるかって思われるでしょう? それが嫌なの。どうせならみんな仲良くやりたいじゃない」
リンさんは微苦笑を浮かべつつ、またカップに唇を寄せた。宮殿に向かう直前に短くしていった髪も、いつの間にかまた伸びている。切りに行く暇もなかったんだろう。髪を耳にかける仕草一つとっても頼もしく見えるんだから、私はもう重症だ。
「だから気にしなくていいのよ、サホ」
何気ない口調で、リンさんは言った。まるで全て見透かされているような一言に、胸の奥がきゅっと縮こまる。
「私、この大袈裟な異名も嫌いじゃないし。ここでこうやって生きてきたことを後悔なんてしてないから」
思わず黙り込んでいると、リンさんはふいと悪戯っぽく笑う。私の気から読み取ったにしては的を射すぎていて、やっぱり敵わないなと再確認してしまった。
「単に私が生きやすい場所にしたかっただけなのよ」
くつくつと笑い声を漏らすリンさんの強さを、真似することなんてできないけど。でもこの場所を守りたいと思うのは私も同じだ。技使いだからとか、女の子だからとか言われない、かわいそうな孤児とも言われない世界。せっかくリンさんが作ってくれたこの居場所を失いたくない。
「わかってますよ。だから心配しないで行ってきてください。この通り、何かを守るのは得意ですから」
「さっすがサホ、頼もしいわね」
ずっと傍で見てきたのだからわかってる。だから寂しいと泣くつもりもなかった。私はただ、いつかリンさんが戻ってくるその日までここを守るだけだ。
その時はちゃんと、リンさんの大好きなお茶を用意しておこう。
神童にさよなら
「シャープさんの淹れるお茶はよい香りがしますね」
席に着いた少女の声が感慨深げに聞こえるのは、私の気のせいだろう。白い棚に手を伸ばした私は肩越しに振り返った。結ぶのが面倒で放ってあった自慢の蜂蜜色の髪が揺れる。
「あら」
普段と変わりない無表情を貫く少女の横顔が、視界の端にちらと映った。暗い灰色のワンピースは顔色を悪く見せるから止めなさいと言っているのに、彼女は今日もそれを身につけている。
「これが趣味だもの当然よぉ。こんなところでできることなんて限られてるんだから、うまくもなるわぁ」
「でも、よい趣味だと思います」
視線を棚に戻せば、お目当てのクッキー缶が見つかった。誰にも見つからないようこっそり奥に隠してあったものだ。それを抱えた私は、華奢な椅子を目指す。
医務室の一角に無理やり設置した白いテーブルセットは、もう何度も撤去するよう言われていた。でも気にしたことはない。医務室といったってできることなんて限られているし、どうせ私はここで食事もすませている。衛生面だのを気にするなら今さらの話だ。
「どうしたの梅花。褒めても何も出ないわよ?」
「正直な感想ですよ、シャープさん。疑り深いですね」
椅子に腰掛けた私は、淹れたばかりの紅茶へ一瞥をくれてから面を上げた。すると白いカップに指を滑らせるようにして、この宮殿の麗しの少女――『ジナルの神童』こと梅花が頭を傾ける。ここで淡く微笑まれたら女の私でもときめくだろうって思うくらいの美少女っぷりだ。
お気に入りのティーセットはどれも飾っているだけで十分素敵だけど、彼女が使うとさらに映える。私が暇を見つけては彼女をこの秘密のお茶会に誘う理由もそれだ。ともすればすぐに心が荒みそうになるこの宮殿で見つけた、数少ない楽しみ。そして目の保養。白や黄のワンピースでも着てくれたら最高だと思う。
忙しい神童を呼び止めることができるのは私ともう一人、彼女の親代わりの一人である青年くらいだと思う。ここを利用する人なんて滅多にいないのも、彼女が快諾する理由の一つだから役得だ。
彼女はいつも人目を気にする。いや、それは正確な表現じゃあないかな。人の目がある場所では常に何かを警戒している。
「疑り深いだなんて褒め言葉よ。この宮殿にいたらそうならなぁい? まぁでも、あなたがそういう類の嘘を吐かないのはわかってる。単なる冗談よぉ」
彼女を前にすると何故か間延びした口調になるのは不思議だ。私も白いカップを手にし、まず香りを味わった。うん、上出来。いい匂い。遠出する理由のない私は、なかなか珍しい茶葉を買う機会に恵まれない。先日久しぶりの休暇だったからはしゃいであれこれ買ってきてしまったんだけど、正解だった。これはよい買い物をした。
「うん、さすがアールのは質がいいわぁ」
口に含むと優しい甘さと酸味が広がる。多忙で荒れ気味だった心も癒される味わいだ。
「ところで。梅花は最近さらに忙しそうじゃない?」
お茶に呼んでおいてこんな質問するのも馬鹿だけど、ずっと気になっていたので遠慮せずに聞いてみる。人使いの荒さにおいて先頭を切って走っているこの宮殿でも、この美少女のこき使われ方は目に余るものがあった。
それが一体いつからなのかは私の記憶でも曖昧だ。まだ十六歳なのに、既に年季が入ってしまうくらいではある。まあどんな難題もこなしてしまう彼女も彼女だろう。無理なものは断ればいいのに……って私に言えることでもないか。この宮殿では、『上』の命令は絶対だ。
「そうですね、忙しいです。引き継ぎもありますし。それに、今のうちにと言わんばかりにみんな仕事を押しつけてくるんですよ。私がここを出るぎりぎりまで利用するつもりなんでしょうか」
カップを片手に梅花は何気ない口調でそう答えた。呆れている様子でもないし、嫌悪している様子でもない。ひたすら淡々としていた。これがこの少女の特徴だし、かわいそうなところだ。――慣れてしまっている。
「なるほど、駆け込みの仕事なのねぇ。そんなんじゃあ無世界に行く準備なんてできないでしょう?」
「いえ、そんなことは。そもそも準備と言われてもほとんど何もする必要がありませんし」
あっさりそう答える梅花の黒い瞳を、私はまじまじと見返した。そして考え込む。確かに彼女ならば何もする必要がないのかもしれない。
この宮殿の奴隷状態だった彼女が、ついに解放される時が来た。神技隊に選ばれたからだ。異世界へと赴き違法者を取り締まるのがその仕事となっているが、実際はそれだけに限らないらしい。私も詳しいことは知らないけれど、複雑なことになっていると聞く。
異世界に行くのには様々な準備が必要だ。だから選ばれた者たちはしばらくの間この宮殿で講義を受ける。異世界の常識の話や文化のこと、また言語について学ぶ。異世界の言語はこちらでいう古語の一種らしい。
この勉強期間が大変苦痛だという噂だが、ジナルの神童は既に全て習得していた。そもそも彼女はその神技隊を選ぶ側の人間だったから、神技隊や異世界の事情については人一倍詳しい。しかも私物へのこだわりも少ないから、準備する必要などほとんどないのだろう。
「なるほどねぇ。だからって仕事押しつけてくるのはどうかと思うけど」
技使いとしても類い希なる力を持っているし、記憶力もいいし頭もよく回る。まさに神童。成長するとただの人になるのが大半と聞いているのに、彼女の場合は伝説が増えるばかりだ。ただ子どもと言える見目ではなくなっただけ。
「いつものことと言えば、いつものことですけどね」
カップに口づけた梅花は、そっと目蓋を伏せた。かすかに揺れる睫毛の長いこと。雪を思わせる肌に、艶やかな黒髪。華奢なのに出るところは出てるし、天は色々なものを与えすぎだと思う。――それは、負の面でもか。
「それもそうかしらねぇ。あ、このクッキー頂き物なの。食べていってね」
缶の蓋を開けて、私はそれをずいとテーブルの真ん中に置いた。お皿に綺麗に並べてもよかったんだけど、この缶も綺麗だからそのまま出しちゃった。深い赤が本当に素敵。
ウィンに出向いた友人からのもらい物だけど、私の趣味をよく理解してくれているみたいだ。金のリボンとの組み合わせを見て、私を想像したらしかった。
「ありがとうございます」
すると梅花は小さく頭を下げる。遠慮深い彼女もお茶会の回数を重ねたおかげで、ようやくこうした場面で頷いてくれるようになった。親という庇護なくこの宮殿の荒波に飲まれた彼女は、どこにいても身構えている。この医務室の中は安全だってわかってもらうまで、ずいぶん時間が掛かった。これも私の努力の成果ね。
「美味しいでしょ? ウィンのものなのよぉ」
こんなお茶会を果たしてあと何回開くことができるのか。そんな風に考えるのはもう止めた。今はただこの恵まれた時間を堪能しよう。そうでなければ、付き合ってくれる彼女にも申し訳ない。
「今度はウィンにも行ってみたいわね」
クッキーを一枚口の中へ放り込み、私は頬を緩めた。
天敵にさよなら
「勝手に入ってきて勝手にくつろぐのってどういうことなんですか」
自分以外誰もいないはずの家の中に、いつの間にか居座っている天敵の顔。それを目にして思わず眉根が寄った。
目映い金髪も青い瞳もこの笑顔と共にあるのを見ると拒否感しか覚えない。たちが悪いのは気を隠していることだ。つまりオレにばれないようにしてる。驚かそうとしている。――完全に嫌がらせだ。
「やあ、アキセ。お邪魔してます」
「ええ、邪魔なので帰ってください、よつきさん。宮殿行きの準備があるって聞いてましたけど?」
「そんなのとっくに終わりましたよ」
よつきというのがこの天敵の名だ。近くに住む技使いというだけで、今まで散々な目に遭ってきた。オレの方が四つ年下というのがいただけない。この四つというのが微妙なところだ。
遊び仲間と言えるほど年が近いわけでもなく、かといって無条件にかわいがってもらえるほど離れているわけでもなく。言うならばオレは奴隷みたいなものだ。技の実験台にされたこともある。「熱をよく吸いそうですね」といって黒髪をくしゃくしゃにされたことは数え切れないほど。おやつを横取りされるのは日常だった。
思い出すだけ気分が重くなり、オレはため息を吐く。まさかこれが二十歳を超えても続くとは想定外だ。
「はぁ、そうですか。それはそれは準備が早いことで」
「アキセ、珈琲はまだですか? ほら、お客さんには珈琲でしょう」
「呼んでもいないのに勝手に入り込んでいる人間を、誰も客とは呼びませんよ。それは侵入者って言うんです」
吐き捨てるようにそう言いながらも台所に向かうんだから、完全に奴隷根性が染みついてしまっている。いやいや、報復が怖いだけだ。日常どこに潜んでいるかわからぬものに怯えながら暮らすのは心臓によくない。それに、全てあともう少しの辛抱だった。あともう少しすれば、この天敵はオレの前からいなくなる。
「いつものでお願いしますねー」
「はいはい」
背後からのほほんと響く声に、投げやりに返してやった。見目は悪くないし身内以外には人当たりのよい青年。そうなだけにオレの嘆きは周囲になかなか理解されない。あの天敵が本性を見せる相手というのは、かなり限られている。今のところ一番扱いがひどいのはたぶんオレだ。
「あともうちょっと」
誰にも聞かれないよう、口の中だけで唱える。よつきさんがついに神技隊に選ばれたと聞いたのは夏の初めの頃だった。神技隊に選ばれた技使いは異世界に派遣される。つまりもう顔を合わせる必要がない。この時をオレはどれだけ待ち望んだことか。
派遣されるのは春だと聞いていたからもうしばらくはこのままかと思っていたところ、その前に宮殿に呼び出されるという事実を知った。異世界について勉強する期間が設けられているらしい。オレが想像していたよりも、別れは案外すぐ近くまで迫ってきていた。
もちろん、よつきさんの新たな被害者が出ないこともちゃんと祈っている。でも基本的に、あの人は他人には優しい。自分が我が儘を言う相手というのを選んでいる。出会ったばかりの人に無理難題を押しつけることはないだろう。
「よし」
考え事をしながらでも準備が終わっているんだから、本当に身に染み込んでるんだなと苦笑しそうになった。カップを二つ手にして、こぼれてもかまわないとずんずん大股で歩けば、テーブルで頬杖をついていたよつきさんはあくびを堪えた。ここまで眠そうな顔というのは珍しい。
「はい、いつものです」
「ありがとうございます」
砂糖を一さじだけ入れた珈琲がよつきさんの好みだ。このこともそろそろ記憶から抹消してもよいのかもしれない。万が一またよつきさんが戻ってきた時? その時は必ず絶交してやる。絶対にだ。
「わたくしがいなくなると、アキセも寂しくなりますねー」
オレが固く決意しているのを知ってか知らでか、よつきさんはのんびりとした口調でそんな風に言ってのける。まるでオレの反論を待ってるかのようだ。返ってくる言葉なんて簡単に予想できるだろうに。
「まさか。その時を楽しみにしてるくらいですよ」
もし、それを期待しての言葉だったら? オレはよつきさんの期待通りに答えていることになる? ちらりと脳裏をよぎったのは、あまり考えたくない可能性だった。
たまにこの天敵がわからなくなる。頭が悪いわけでも常識がないわけでもないのに、あえてこう振る舞っている理由に疑問が生じる。楽しいんだろうか。
オレはいつもの席に腰掛け、大袈裟に肩をすくめた。
「準備ができたならさっさと宮殿に行ってください」
半眼になったまま珈琲カップに手を伸ばせば、少し心が慰められる。今日は無糖。何故だか苦いのが飲みたい気分だった。伸びつつある髪を耳にかけて香りを吸い込むと、胸の奥から何かが温められる。体が芯からほぐれていく。
「アキセは相変わらずつれないですねー」
「誰のせいだと思ってるんですか」
この憎まれ口を聞くのもいつまでだろう。よつきさんのけらけらとした笑い声を耳にしながら、オレはそっと珈琲カップに唇を寄せた。